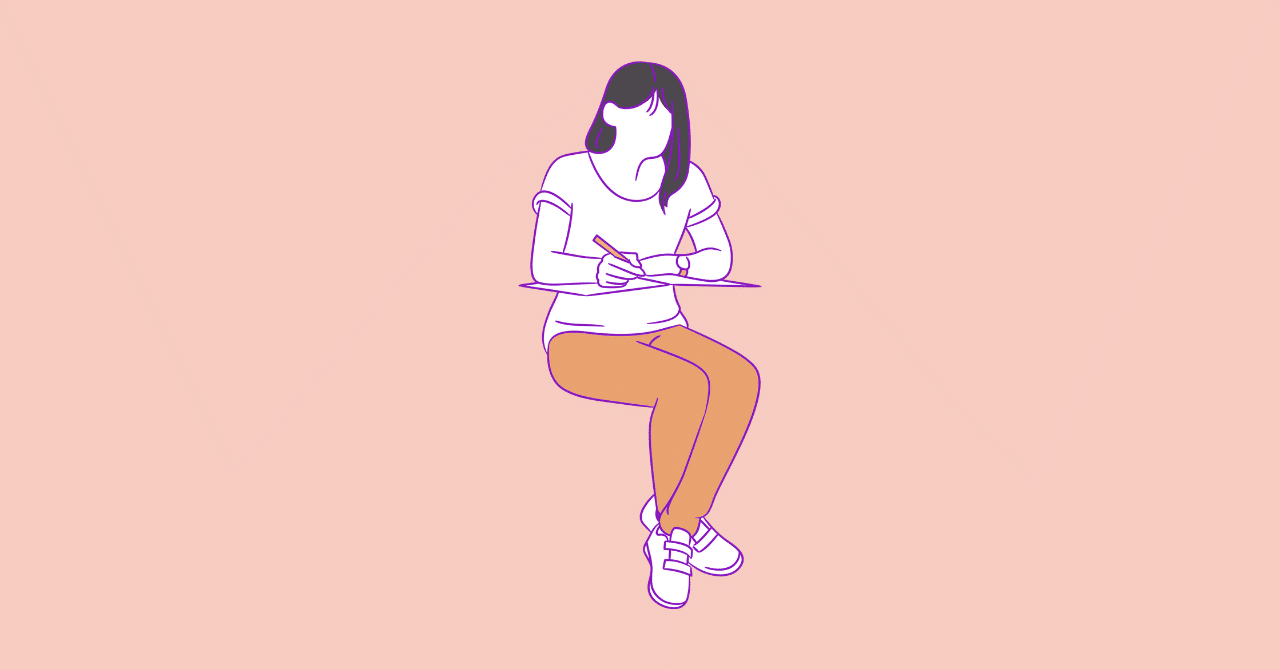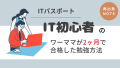仕事を辞めたい。でも、お金のことを考えると踏み出せない。
そんなふうに迷いながら働き続けているワーママは、決して少なくありません。
「貯金ってどのくらい必要?」
「失業保険はもらえるの?」
「扶養に入れる?」
わたし自身も退職を決めるまで、生活費や保険、税金のことが心配で、何度も検索して調べました。
けれど、不安の正体を“見える化”していくうちに、少しずつ不安の原因がはっきりとして、退職を決める決断ができました。
この記事では、そんな私が実際に退職前に準備しておいてよかった「お金まわりのこと」を7つにまとめてご紹介します。
辞める・辞めないをすぐに決める必要はありません。
けれど、備えておくだけで安心できることが、意外とたくさんあります。
まずは、自分の不安をひとつずつ整理してみませんか?
退職後に備える「お金のこと」
退職後の不安は、“見える化”することで、少しずつ原因がはっきりしてきます。
退職後の生活をイメージし、備えておくことでその不安に備えることができます。
貯金、保険、税金、失業保険、扶養。
考え始めるとキリがありませんが、不安の元になりやすい項目を整理して、「見える化」すること。
事前の準備があれば、退職を「前向きな選択」に変えられます。
私も「お金が不安」で、しばらく動けませんでした
退職を考えていたあの頃、いちばん怖かったのは「この先どうなるかわからない」ことでした。
私の収入がなくなっても、本当にやっていけるのだろうか。
今の貯金で足りる?
教育費は?
家のローンは?
考え始めると、不安ばかりが頭をよぎっていました。
正社員として働いているときは、共働きであることに安心しきっていて、毎月の収支もぼんやりとしか見ていなかったと思います。
でも退職を決める前に、家計簿アプリで支出を見える化し、退職金や失業保険の制度を調べて、FP(ファイナンシャルプランナー)に相談してキャッシュフロー表を作ってもらいました。
ひとつずつ確認していくなかで、「辞めてもなんとかなるかもしれない」と思えるようになりました。
不安の正体が見えてくると、気持ちは少しずつ前を向きはじめます。
これは、私自身が実感したことでした。
退職前にやってよかった「お金の準備」7つ
私が退職前に実際に取り組んだ「お金まわりの備え」を7つご紹介します。
地道な準備でしたが、『辞めてもやっていけるかも』と思える支えになりました。
貯金の「見える化」と、生活費6ヶ月分の目安を知る
再就職まで少し時間が空く可能性があるなら、まずは生活費の6ヶ月分を確保できるか確認を。
そのためにも、今の資産と支出を“見える化”することから始めましょう。
- マネーフォワードME (無料でも十分便利)
- Zaim(シンプルな操作感で使いやすい)

「思ったより使ってた…」という気づきが、不安を現実的に整理する第一歩になります。
退職金の有無と振込タイミングをチェック
退職金があるかどうか、いくら出るのか、いつ振り込まれるのかは就業規則で確認できます。
わからない場合は、人事に「退職手続きについて教えてください」と聞くのが自然です。
概算がわかったら、FP(ファイナンシャルプランナー)に相談してキャッシュフロー表を作成してもらうのもおすすめ。
無料でWeb面談できるサービスもあり、退職後の資金計画が立てやすくなります。
退職後も続く固定費(保険・年金・住民税)を把握する
退職しても、以下の支払いは続きます。
- 健康保険料(社会保険任意継続 or 国民健康保険)
- 国民年金(約1.7万円/月)
- 住民税(前年の年収に基づき請求)
特に健康保険料は、選択によって負担額が大きく変わるため、比較してから手続きしましょう。
退職後の出費を見落とさないことが安心材料になります。
通信費・サブスク・光熱費などの固定支出を見直す
退職直後は収入が不安定になることも。
だからこそ、固定費の見直しは「できる節約」としておすすめです。
- 格安SIMに変更
- 使っていないサブスクの解約
- 電力会社のプランを見直し
特にサブスクはチリツモで家計に響きます。「これは本当に必要?」と見直す機会にしましょう。
失業保険の条件と給付タイミングを確認する
自己都合退職でも、雇用保険に1年以上加入していれば失業保険を受給できます。
ポイントは以下の3点です。
- 2025年4月以降、給付制限が2ヶ月→1ヶ月に短縮
- 給付までの生活費は現金で1ヶ月分を準備
- 職業訓練に通えば、給付制限なし+訓練中も支給あり
私は職業訓練制度を利用して、安心してスキルアップに集中できました。
(参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます)
配偶者の扶養に入れるか、早めに確認する
退職後に配偶者の扶養に入れば、保険料の負担を大幅に減らせることもあります。
ただし、以下に注意が必要です。
- 退職後、すぐに働く場合は扶養の壁に注意
- フリーランスや副業収入があると審査が厳しくなることも
- 失業保険の金額によっては、扶養に入ることができない
私は失業保険の受給額が理由で、扶養には入れませんでした。

事前に配偶者の勤務先に確認しておくのが安心です。
不安は一人で抱えず、信頼できる人に相談する
退職後のお金の不安は、一人で抱えているとどんどん大きくなってしまいます。
私は無料のFP相談を活用して、家計やライフプランを見直すことができました。
- マネードクター(無料でキャッシュフロー表を作成)
- ほけんのぜんぶ(保険の見直し相談にも対応)
相談をきっかけに、“大丈夫かもしれない”と思えるようになりました。
まとめ|退職は、備えることで前向きな選択になる
「辞めたいけど、お金のことが心配で動けない」
仕事と育児の両立に限界を感じていても、漠然とした不安から動けずにいる人も多いのではないでしょうか。
でも、不安の正体をひとつずつ見える化して、地道に備えていくことで、退職は「後悔しない選択」に変わっていきます。
今回ご紹介した7つの備えは、今日からでも始められることばかりです。
できるところから、少しずつ手をつけてみてください。
お金の不安が和らいでくると、きっと気持ちも前を向けるようになります。
「辞めても、なんとかなるかもしれない」
そんなふうに思える日が、あなたにも訪れますように。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
- 家計管理 |マネーフォワードME、Zaim
- 通信費節約 |楽天モバイル、UQモバイル など
- FP相談 |マネードクター、ほけんのぜんぶ
【関連記事】
👉ワーママを辞めても大丈夫と思えた資産のつくり方